前回、大岡昇平の「現代小説作法」ちくま学芸文庫を紹介しました。
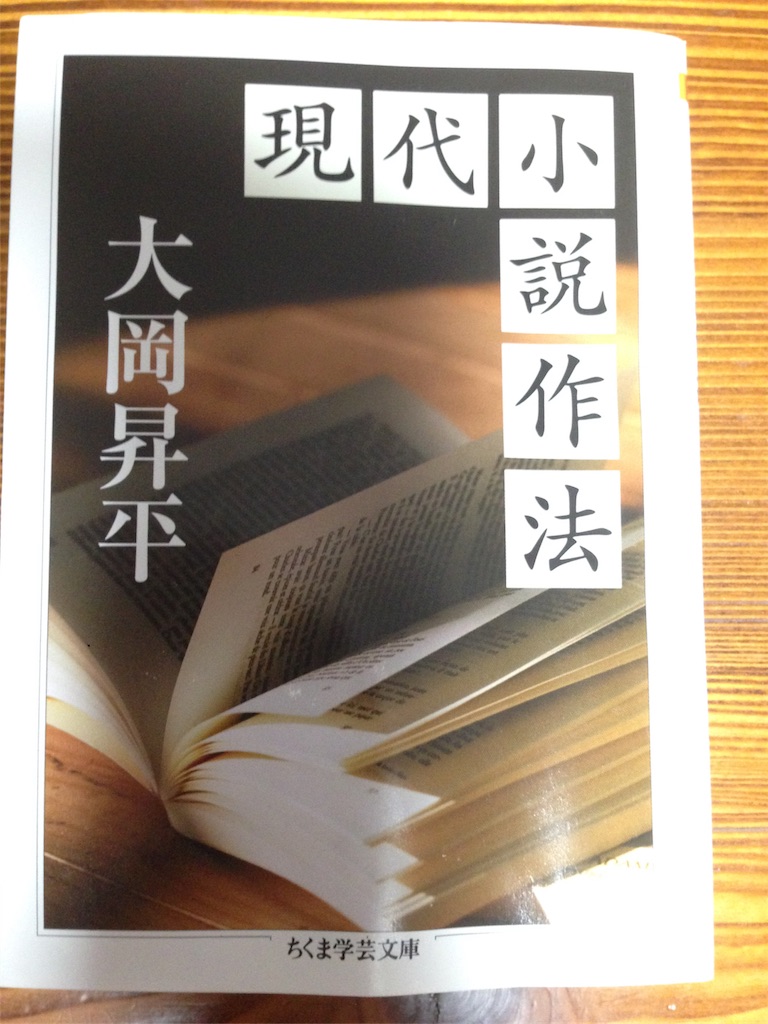
今回も、続いて紹介します。武庫川女子大学の他に、2017年の国士舘大学でも出題されていたのを見つけたからです。
国士舘大学では、「現代小説作法」の第二十二章 「文体について」が問題文として使われています。ちくま学芸文庫の217ページから220ページの8行目まで。このあと、226ページまで続くので、省かれた部分が多いです。
文体について、参考になる箇所を引用します。
文章はいかに美しく、無疵に書かれるかより、たしかにあの人が書いた文章だ、あの人でなくちゃ書けない文章だ、と思われる方が尊敬されるようになった。破格な調子の悪い文章も、その人の特徴を示すものとして、尊ばれたのです。
よき日本語を、よい文章を、と言う理想が、明治以来西欧のロマンティシズムに感染した文人に、どの程度あったか疑問です。漱石がアテ字や俗語を、勝手気儘に使ったのは周知のことですし、鴎外が字引にないような稀語難字を好んで使い、外国語はたいてい横文字のまま挿入しました。読者が理解しようがしまいがどうでもいいので、人の知らないことを知ってる自分というものを、読者に示すのに、むしろ誇りとよろこびを感じていたようです。彼らは人生と文学の理想を追うのに忙しかったので、文章の風格とか品とかいうものがやかましく言われるようになったのは、大正以来のことなのです。
身もふたもない意見ですね。この章から文体の作り方など創作の秘訣を学ぼうとしても残念ながら無駄です。 書かれていませんから。
入試問題で取り上げられていない後半の部分では、森鴎外、谷崎潤一郎、太宰治、島崎藤村が引用されています。いずれも悪口まではないにしても、決して高く評価しているわけではありません。しいていえば、disっている感じでしょうか。
大岡昇平はなかなか有名作家には厳しいのかな。さすがに大学は、この部分は使っていません。いや、使えないでしょう。
国士舘大学の入試問題の設問は、語句の意味や文学史など知識を問うものが中心で、深く掘り下げた設問はありません。その意味では難しい問題ではないでしょう。